
“ちゃんと休む”って、どういうことか誰も教えてくれなかった
“休み下手”は、あなたのせいじゃない
「せっかくの3連休なのに、なぜか休んだ気がしない」「日曜の夜が怖い」。そんな思いを抱えたまま、また1週間が始まっていく──。あなたもそんな経験、ありませんか?
それは決して、あなたが「休み下手」だからではありません。むしろ、“休む”という行為そのものが、あまりにも曖昧で、属人的で、誰にも教えられてこなかったからです。
日本人は、「働き方」にはうるさくても、「休み方」については無関心です。小学校でキャリア教育は受けても、休暇教育は受けません。大人になっても、「休むことは悪」「休むことは迷惑」といった空気が残る社会で、私たちは“休むことの意義”すら見失ってしまいました。
「休み」が変わった、コロナ禍を経て。
2020年のパンデミックは、私たちの生活や働き方だけでなく、「休み方」の常識にも一石を投じました。
・出勤しなくても仕事はできる ・家にいるからといって、心が休まるわけではない ・仕事とプライベートの境界があいまいになると、回復できない
こうした経験から、多くの人が気づきはじめました。「あれ? 自分、何のために休んでるんだろう?」と。人は休まなければ壊れます。でも、ただ寝るだけでは回復できない。休みにも、設計が必要なのです。
他人の休み方は参考になるのか?
よくある世界の一流エグゼクティブの生活の休み方から学びと気づきを得ることを目的とした本。仕事を成功させるための「自己投資」や「成長志向」に休日を絡められても、「私はどうありたいのか」「私にとっての回復とは何かという“内面の価値観”とつながる必要性が欠けているので、どこかモヤモヤが残ってしまう。
休み方には「目的意識」と「能動性」がある
私たち「休日デザイン研究所」では、休み方を次の2軸で分類する“ホリデータイプ4象限モデル”を提唱しています。
-
縦軸:「目的意識」── 休むことに明確な目的があるか?
-
横軸:「能動性」── 自ら選び取って休んでいるか?
これにより、たとえば以下のように分類されます:
|
能動的 |
受動的 |
|
|
目的意識あり |
家族旅行、趣味、仕事の原動力となる活動 |
子どもの授業参観、PTA、親の通院付き添い |
|
目的意識なし |
1人で衝動的に日帰り旅、カフェ巡り、あまり興味のない映画などに連れていかれる |
SNSをだらだら、YouTubeで夜ふかし |
どれが良くて、どれが悪いという話ではありません。大切なのは、自分が「どのタイプ」にいるのかを知り、次の休みにどう活かすかです。
「休む」ことは、UX設計である
多くの人が「休みたい」と言いながら、実際に休んでも疲れがとれなかったり、満足感を得られなかったりします。それは「休み」を感覚任せで過ごしているからです。
UX(ユーザー体験)デザインの視点で言えば、「どうすれば自分にとって心地よい休みになるか」を構造化し、計画・習慣化していくことが鍵になります。
休み方は、「見える化」で変わる
現在、私たちが開発しているのが「ホリデータイプ診断」や「休み方偏差値」の可視化ツールです。
-
自分がどの象限にいるか?
-
偏差値でどれくらい“休めている”のか?
-
どのタイプと相性が良いか?
こうした診断を通じて、自分の休み方を“言語化”し、次の行動へつなげていくことが可能になります。これは単なるエンタメではなく、自己回復力のトレーニングなのです。
休み下手は、あなたのせいじゃない
「ちゃんと休みなさい」と言われても、何をすればいいか分からない。「好きにしていい」と言われても、逆に不安になる。
そんな時代に、「休む」ことは、私たち一人ひとりが見つめ直すべき“人生の設計”そのものになっています。
休み方は、誰かの真似ではなく、自分自身の価値観と連動して初めて力を持ちます。エリートの模倣ではなく、“私らしい休み”をデザインする。それが、休日デザイン研究所の提案です。
あなたも、次の休日に問いかけてみてください。
「この休み、誰のため? 何のため?」
答えは、あなたの中にあります。
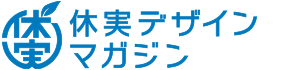





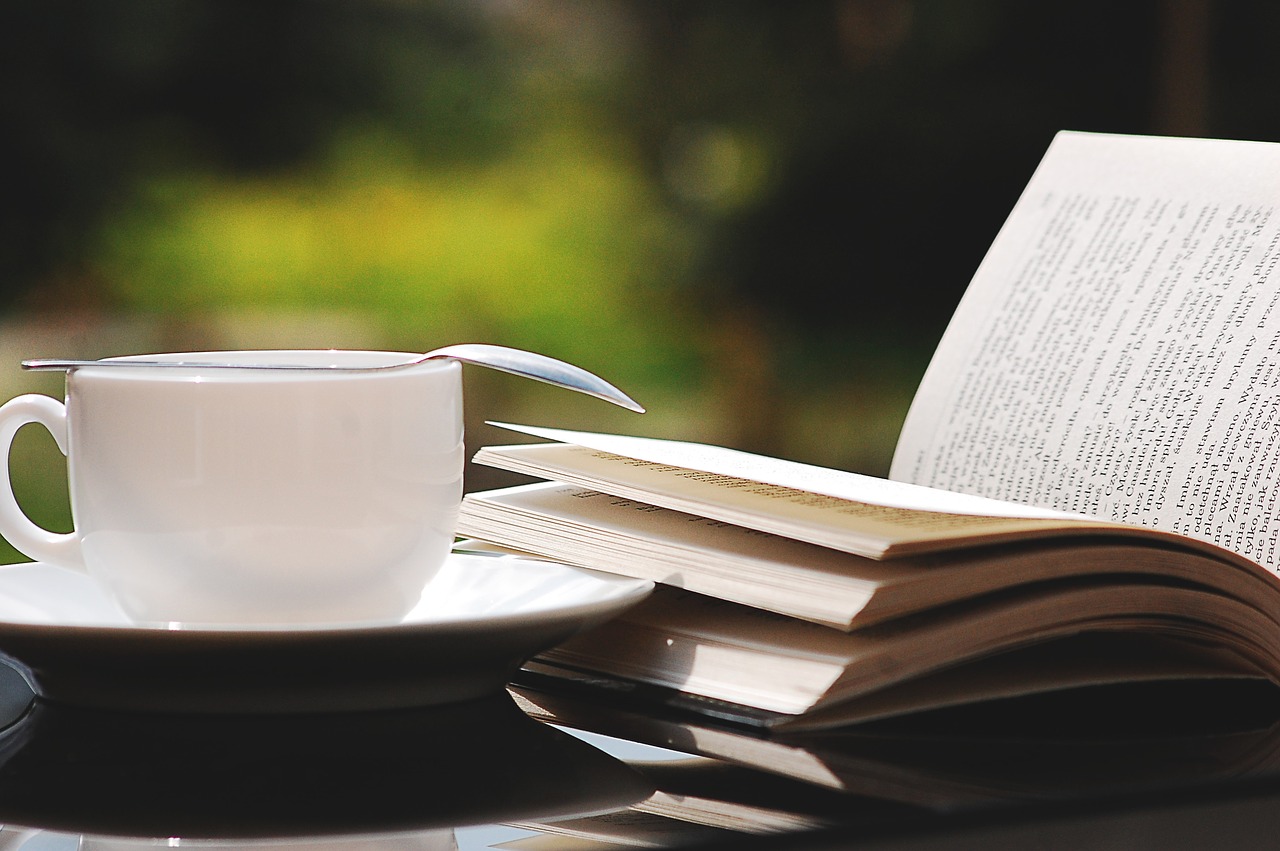





























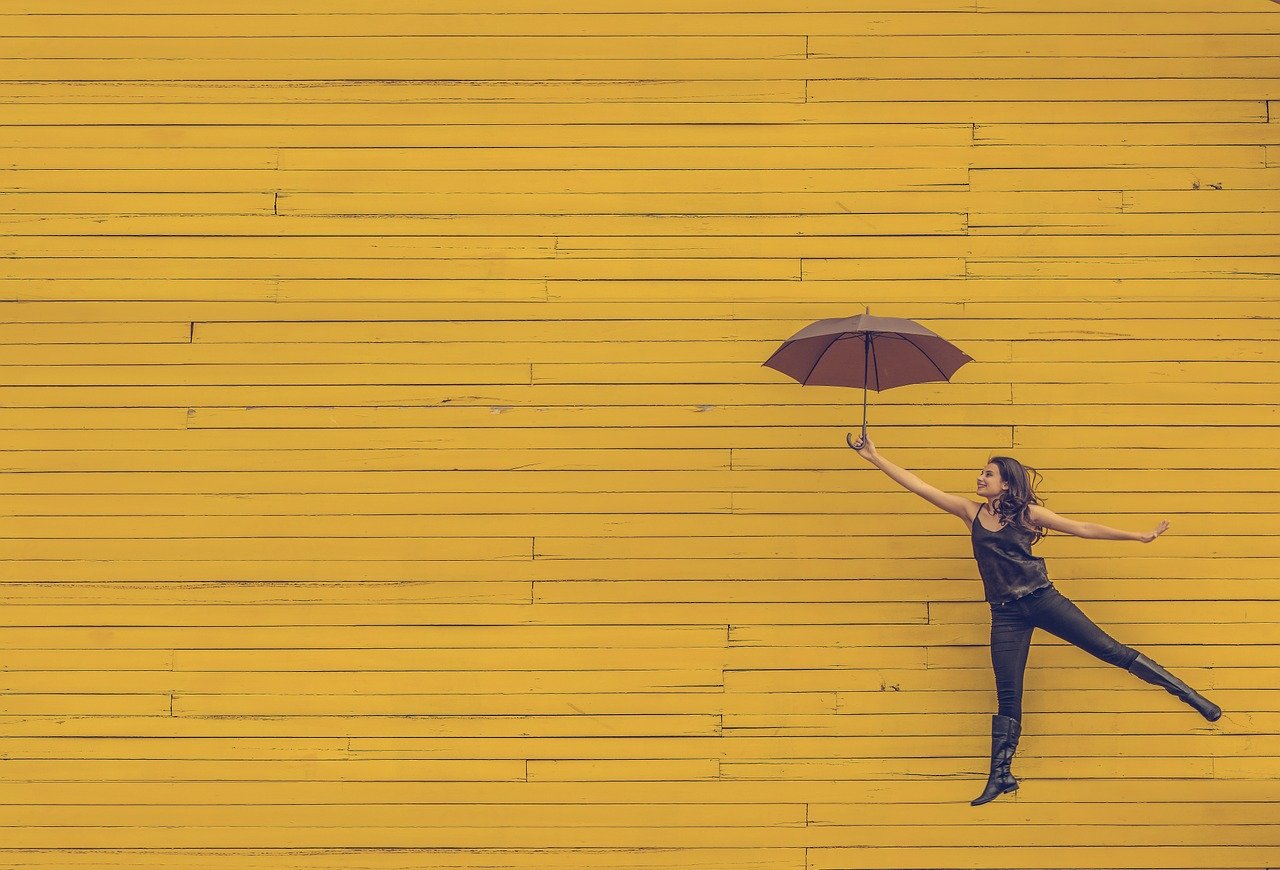
この記事へのコメントはありません。